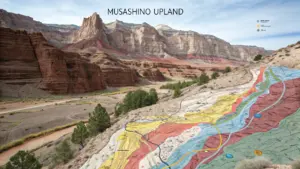「品川駅は品川区にある」と思っていませんか。
実は多くの人が利用する品川駅の本当の所在地は港区で、この事実には歴史的な理由が隠されています。
この記事では、なぜ品川駅が品川区にないのか、その背景にある「鉄道ができた明治時代の歴史」と「後の行政区分の変更」という2つの理由を、地図を交えながら分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 品川駅の本当の所在地
- 品川駅が品川区にない2つの歴史的な理由
- 目黒駅など他の駅名と住所が違う例
品川駅が品川区にないという意外な事実
通勤や旅行で多くの人が利用する品川駅ですが、その所在地を正しく知っていますか。
「品川」という名前のため、もちろん品川区にあると思われがちですが、実は品川駅の本当の所在地は港区です。
この意外な事実には、鉄道が走り始めた明治時代までさかのぼる歴史的な背景が隠されています。
品川駅の所在地は東京都港区高輪
品川駅の正式な住所は「東京都港区高輪三丁目」になります。
JR東日本やJR東海、京浜急行電鉄が乗り入れる巨大なターミナル駅ですが、その敷地はすべて港区内に収まっています。
毎日約25万人以上が利用する駅にもかかわらず、駅名と住所が違う事実はあまり知られていません。
品川駅の南側がすぐ品川区との境界線になっており、この地理的な関係が長年の勘違いを生む一因となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駅の正式住所 | 東京都港区高輪三丁目 |
| 設置者 | JR東日本・JR東海・京浜急行電鉄 |
| 所属行政区 | 港区 |
この「港区高輪」という住所こそが、品川駅にまつわる謎を解き明かすための出発点となるのです。
駅名と住所が異なる理由の概要
駅名と実際の住所が異なる理由は、主に「歴史的な背景」と「後の行政区画の変更」という2つの要因が関係しています。
決して間違いや偶然でこうなったわけではありません。
駅が開業した明治5年(1872年)当時、駅が建設された場所は江戸時代の宿場町「品川宿」の玄関口にあたる場所でした。
その後、昭和22年(1947年)に行われた行政区画の再編により、駅のあるエリアは港区に、旧品川宿があったエリアは品川区へと分かれたのです。
| 理由 | 概要 |
|---|---|
| 歴史的背景 | 鉄道開業時、旧東海道の宿場町「品川宿」の玄関口に設置されたため |
| 行政区画の変更 | 1947年の区画再編で、駅のある高輪エリアが港区に編入されたため |
つまり、駅の名前は歴史的な地名に由来し、住所は現代の行政区画に基づいているため、このような「ねじれ」が生まれています。
品川駅が港区に存在する2つの歴史的経緯
駅名と実際の所在地が違うという、少しややこしい状況が生まれた背景には、駅ができた明治時代の歴史と、その後の行政区分の変更という2つの理由が大きく関わっています。
歴史的な地名が駅名として採用された後、行政上の境界線が変わったことで現在の形になりました。
経緯1 鉄道開業時の設置場所が旧品川宿の玄関口
品川駅の名前の由来を語る上で欠かせないのが、江戸時代の宿場町「品川宿」の存在です。
品川宿は、東海道五十三次における最初の宿場町として、多くの旅人で賑わっていました。
1872年(明治5年)の鉄道開業時、駅が建設されたのは品川宿の北のはずれでした。
江戸の中心地から見れば、まさに「品川宿への玄関口」にあたる場所だったのです。
開業当時の住所は「芝区高輪南町」であり、この時点ではまだ港区も品川区も存在しませんでした。
多くの人にとって馴染み深い「品川」という地名が駅名として採用されたのは、こうした歴史的背景があったからです。
経緯2 後の行政区再編による所在地の変更
時代が下り、1947年(昭和22年)に行われた行政区分の再編が、現在の所在地の決定的な理由となりました。
この再編で、東京23区の原型が作られます。
このとき、品川駅があった高輪エリアを含む旧「芝区」は、麻布区、赤坂区と合併して現在の港区になりました。
一方で、宿場町だった品川宿のエリアは、旧品川区と旧荏原区が合併し、現在の品川区が誕生したのです。
駅の名前は歴史に由来する「品川」のまま残りましたが、行政上の境界線が変更されたことにより、駅の所在地だけが港区に取り込まれる形になったのです。
地図で確認する品川駅と品川区の位置関係
言葉だけでは少し分かりにくいかもしれませんが、地図を見ると品川駅と品川区の位置関係はすぐにわかります。
実は、駅の敷地のすぐ南側が港区と品川区の区境になっており、目と鼻の先に品川区があるのです。
駅周辺の地名や、歴史的な中心地を知ることで、この位置関係がより深く理解できます。
駅のすぐ南側が港区と品川区の境界線
品川駅の正式な住所は、東京都港区高輪三丁目です。
地図で確認すると、品川駅のホームの南端を横切るように港区と品川区の境界線が引かれています。
例えば、山手線のホームの一番南側、京急線の乗り換え通路を過ぎたあたりがちょうど区境にあたります。
電車が駅を出発して数秒で、行政区をまたいでいることになります。
駅周辺の地名「高輪」と「港南」
品川駅には、西側の「高輪口」と東側の「港南口」という主要な出口があります。
この出口の名前が、そのまま駅がまたがるエリアの地名を示しています。
高輪口側はホテルや閑静な住宅街が広がる港区高輪、新幹線乗り場のある港南口側はオフィスビルが立ち並ぶ港区港南です。
駅は、港区の「高輪」と「港南」という2つの街に挟まれる形で存在しています。
かつての品川の中心地、北品川駅周辺
では、歴史的な「品川」の中心はどこかというと、それは京急本線の北品川駅周辺です。
このエリアこそ、江戸時代に東海道最初の宿場町として栄えた「品川宿」があった場所です。
品川駅から南に徒歩10分ほどの場所にありますが、駅名は「北品川」という点も興味深いところです。
今でも旧東海道沿いには、当時の面影を感じさせる街並みが残っています。
品川だけではない駅名と住所が異なる東京の駅
品川駅のように、駅名と実際の所在地が一致しないケースは東京では珍しくありません。
特に山手線沿線には、地名の境界線が複雑に入り組んでいる場所がいくつか存在します。
| 駅名 | 所在地 | 所在区 |
|---|---|---|
| 目黒駅 | 品川区上大崎 | 品川区 |
| 大崎駅 | 品川区大崎 | 品川区 |
| 五反田駅 | 品川区東五反田 | 品川区 |
駅名だけで所在地を判断すると、思わぬ勘違いをしてしまうことがありますね。
代表例である品川区所在の目黒駅
駅名と住所が異なる最も有名な例として挙げられるのが、JR山手線や東急目黒線などが乗り入れる目黒駅です。
駅名に「目黒」と入っているため目黒区にあると思われがちですが、実際の所在地は東京都品川区上大崎二丁目・三丁目になります。
この事実も、友人との会話で盛り上がる雑学ネタとして知っておくと面白いです。
品川区にある主要駅、大崎駅と五反田駅
一方で、駅名と所在地が一致している品川区の主要な駅ももちろん存在します。
その代表が大崎駅と五反田駅です。
山手線のターミナル駅でもある大崎駅は品川区大崎一丁目に、五反田駅は品川区東五反田一丁目・二丁目にそれぞれ位置しており、品川区を代表する駅として機能しています。
このように、品川駅や目黒駅のような例がある一方で、多くの駅は駅名通りの場所にあります。
駅名の由来を調べてみると、その土地の歴史が見えてきて興味深いですよ。
まとめ
この記事では、多くの人が利用する品川駅が、なぜ品川区ではなく港区にあるのかを解説しました。
その理由は、鉄道ができた明治時代の歴史と、後の行政区分の変更という2つの歴史的経緯が重なった結果です。
- 品川駅の本当の所在地は港区高輪
- 理由は鉄道開業時の歴史と後の行政区分の変更
- 目黒駅が品川区にあるなど他の事例も存在
品川駅を利用する際には、ぜひこの豆知識を思い出してみてください。
友人との会話のネタにしたり、駅名と住所が違う他の駅を調べてみたりするのも、新しい発見があって面白いですよ。